私はこの本を中3の時、兄の薦めで読んだのですが、この時受けた衝撃を今でも忘れられません。ラストの父の話の所を読んでいると、突然視界がぼやけて文字が読めなくなったのです、何が起こったのか分からないくらい涙が滴り落ちていたのです・・まさか自分が本でここまで泣くとは思いもしなかったのです。 私はそれまで小説をほとんど読んだことなく、本に多少偏見を持っていたのですが、この本を読んで180度考えが変わりました。本は人の心を豊かにし、本を読んでいる間はその本の主人公になり、普段体験できない事も読んでいる間実現可能なのです。 私は本当にこの本が気に入り高校に行っても、友人に薦めたのですが、 『今では共感できない。中学生の時読みたかった・・』と言われたのを今でも覚えています。 私はすごくショックでした。 その時、本は読む時期が凄く大切であると実感しました。 ですから、今中学生の皆様、どうか15歳までにできれば読んでいただけば幸いでございます。 それ以上の歳になっても楽しめますが、特に中3の時読めば、一生大切にしたい本になると思います
いちご同盟 (集英社文庫) 関連情報
70年安保でマルクスの洗礼を受けた著者が、40年の時を超えて
比喩を交えながらマルクス経済学を解説しているということ自体が、
面白い。
現在の経済的状況のもとで、『マルクスの夢は貧富の格差のない
豊かな社会の実現と、すべての人に疎外のない充実した人生を与える
ことだった。つまりは生きる目的、生きる希望が必要なのだ。』と
語っているのもナンだか皮肉っぽい。
農業共同体を再構築し、マルクスが目指した疎外なき労働社会を
実現しよう! カネがすべてじゃないじゃないか、生きがいのある
人生こそ最良のものだ。いまこそマルクスの復権を!と言っているのは
カネの亡者が跋扈する現代社会への痛烈な批判‥。(?)
著者の真意は不明だが、その辺が三田誠広らしい。
マルクスの逆襲 (集英社新書 494B) 関連情報
タイトルは「父親が〜」となっていますが、母親にも役立つ内容だと思いました。理数系の基礎というのは、「苦手意識」があるかないかで興味関心が大幅に狭まってしまうもの。子供には不用意な苦手意識を持ってほしくないと思ってきましたが、問題は親の意識でした。この本を読んで「算数って結構面白かったんじゃないの」と感じることができたので、子供にもそれを伝えることができそうです。もっと早く算数が好きになれていたら、きっといろんなことが違っていたでしょう(笑)。 父親が教えるツルカメ算 (新潮新書) 関連情報
 ユダの謎キリストの謎―こんなにも怖い、真実の「聖書」入門 (ノン・ブック)
ユダの謎キリストの謎―こんなにも怖い、真実の「聖書」入門 (ノン・ブック)
この本は、わずか200頁強の本でありながら、イエスとイエスの教団、イエスの教えに肉薄しようという三田のいつも通りの野心的試みである。
三田は、作家らしく、ルカ、マタイ、マルコ、ヨハネの四つの福音書および戦後発見された「トマスによる福音書」「死海文書」の内容のズレから、真のイエスの姿に迫ろうと試みる。若き頃から腐敗・形骸化したユダヤ教の分派を批判し、それがもつ強烈な民族主義を超えて“普遍的な人間の苦悩”の解決のために行動するイエスの姿がまるでそこにいるかのように描かれている。また、十二使徒の一人一人の姿も実に生き生きしていて読んでいて楽しくなる。
『予言書「イザヤ書」に書かれる“屠り場に引かれる子羊”、“彼は自らを償いの捧げ物とした”という部分こそ、キリスト教の宗教原理の根幹であり、イエスは自分自身を「生け贄の子羊」として捧げ、神と新たな契約を結ぼうとした。それこそがキリスト教の教典が「新約聖書」と呼ばれる理由』らしい。
三田はここで大胆な仮説を立てる。熱心党のリーダー格であり、イエスの教団への資金供給を行いと教団のNo.2で会計係でもあったユダは、ローマ帝国支配打倒への意志を示さないイエスを利用できないと最終的に判断したというのだ。最後の晩餐でイエスに「なすべきことをなせ」と言われ、静かに席を立つユダ。神殿兵への連絡、イエスだけの逮捕。そしてゴルゴダの丘でのイエスの処刑・・・。(イエス処刑後数十年経って熱心党は第一次ユダヤ戦争と呼ばれる大反乱を起こしている。)
イエスにはもちろん“殉教の覚悟”というものが常にあったのは想像に難くない。しかし、わずか30歳でその生涯を本当に終えようとしたのだろうか。一人でも多くの人を救うために数々の困難も克服してきた、強靱な生命力と精神をもつ彼は生きられる限りは生きようとしたのではないか・・・。春の朧夜に僕はじっと目を凝らして考え続けている。
ユダの謎キリストの謎―こんなにも怖い、真実の「聖書」入門 (ノン・ブック) 関連情報
 書く前に読もう超明解文学史 ワセダ大学小説教室 (ワセダ大学シリーズ) (集英社文庫)
書く前に読もう超明解文学史 ワセダ大学小説教室 (ワセダ大学シリーズ) (集英社文庫)
著者は母校の早稲田大学で「小説創作」の講師を務めており、そこでの講義を本に
まとめたのがワセダ大学小説教室シリーズ。本書はその三冊目にあたる。純文学を
書きたい若者のために近代日本文学の変遷を学ぶことで、創作に活かしてほしいと
いうものである。著者は「文学史を学べばアイディアは無限」と語る。もちろんそんな
野心のない人にも読み物としてじゅうぶんに面白い。「ものすごーくわかりやすく説明
します」と述べるように、硬くないので文学史のおさらいとしても、楽しく読めるだろう。
あくまで団塊世代の著者の目を通した文学史なので、日本文学の東西の横綱に大江
健三郎と中上健次を選ぶなど違和感もあるかも知れないが、この世代の「文学」への
熱き想いは感じられる。昔は純文学はインテリの中心的話題のひとつだった。いまは
なかなか売れないそうである。明治から20世紀までの時代を創った作家の粗方を網羅
しているのでブックガイドとしても使えるし、著者の評論もユーモアに富んでいて面白い。
大変に好意的に取り上げられてる作家あり、ちょっと意地悪に書かれてる作家ありで、
心の中でツッコミを入れつつ読んだ一冊だ。巻末には著者によるインタビューも掲載。
書く前に読もう超明解文学史 ワセダ大学小説教室 (ワセダ大学シリーズ) (集英社文庫) 関連情報








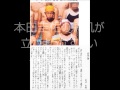




![Ensiferum - Unsung Heroes (Full album HD) [2012] Ensiferum](http://img.youtube.com/vi/Srry38HR2MQ/2.jpg)

![[C9]シャドウダッシュ講座 植田まさし](http://img.youtube.com/vi/W0Sv0GLTIJ8/2.jpg)
![Shito Raisan ~Kamisama to Unmei Kakumei no Paradox [OST] - 使徒礼賛 礼賛](http://img.youtube.com/vi/uyOvxkf4kzA/3.jpg)




![【Amazon.co.jp限定】ストライク・ザ・ブラッド OVA 後篇<初回生産限定版> (前・後篇連動購入特典:「描き下ろしOVA前・後篇収納BOX」引換シリアルコード付) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】ストライク・ザ・ブラッド OVA 後篇<初回生産限定版> (前・後篇連動購入特典:「描き下ろしOVA前・後篇収納BOX」引換シリアルコード付) [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B013T094GI.09.MZZZZZZZ.jpg)

![華名 マニフェスト Final [DVD] 華名 マニフェスト Final [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B010OQECWQ.09.MZZZZZZZ.jpg)




![宝島 2015年 10 月号 [雑誌] 宝島 2015年 10 月号 [雑誌]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B010TMIICK.09.MZZZZZZZ.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ダークナイト ライジング ブルーレイ スチールブック仕様/完全数量限定 [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】ダークナイト ライジング ブルーレイ スチールブック仕様/完全数量限定 [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B014H76CN0.09.MZZZZZZZ.jpg)